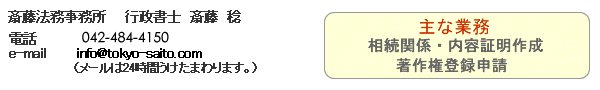| プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。 |
|
|
|
 |
|
|
|
| ■ |
少額訴訟
|
60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されます。通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な処理手続きが用意されています。
内容証明郵便では動かなかった相手も、訴訟になると、反応も違ってきます。
かなり圧力かかりますので、訴状が届いただけで返済してもらえることもあります。
また、簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけで簡単です。
少額訴訟は、あなたと、相手、裁判官、書記官または司法委員が、法廷で簡単な応酬をした後、小部屋で普通の話し合いのように行われます。
法定では、通常、正面(裁判官席)に向かって左側があなた、右側が相手です。
小部屋では、先程まで裁判官席で「ぶっきらぼう」な態度(!?)に見えた裁判官が、普通のアドバイザーとして応対してくれますので、あなたは納得できるはずです。
|
|
少額訴訟のメリット
|
|
(1)簡単
(2)確実(仮執行宣言がつくので、強制執行できます)
(3)早い(審理そのものが1日でおわります)
|
|
少額訴訟のデメリット
|
|
(1)控訴できません。
(2)相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性があります。
|
|
少額訴訟の注意点
|
|
60万円以下の金銭請求のみです。
金銭の支払い以外の物を請求することはできません。
債務不存在確認請求はできません。
訴額が60万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象になりません。
同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできません。
相手方の所在が解らないと、少額訴訟を起こすことができません。
提訴後にあなたから通常訴訟での審理を請求することができません。
相手が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行されます。
あなたと相手ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することはできません。
反訴はできません。
時効が来てしまっていたら、敗訴になる可能性があります。
あなたか、相手が会社だったら、商業登記簿膳本(申請3ヶ月以内のもの)が必要です。
訴訟は、制度の趣旨として、相手が来やすい所ということで、相手の住所地の簡易裁判所で行うのが原則ですが、あなたの住所地の簡易裁判所に提出しても認められます。
その際、相手方に裁判所から「裁判所の変更はできますよ」 という文面が「呼び出し」と同時に送られます。相手が嫌がれば変更もありえますが、審理日が数ヶ月先になる可能性があります。そこで、審理が先延ばしされるのがいやな場合、あまり遠方でなければ、始めから相手の管轄簡易裁判所で行うのも大事なことかと思います。
勝訴判決と債権回収とは別のものであり、「勝訴判決=債権回収できる」では、ありません。
裁判官や司法委員の人が分割払い案や支払猶予などを求めてくる場合もありますし、敷金回収などでも、「ここのところは妥協しましょうよ」と歩み寄りを求めてきたりします。
|
|
少額訴訟の証拠と証人
|
|
証拠
証拠はもちろん、あった方が良いですが、なくても諦める必要はありません。
訴訟をおこすと、相手が、認める場合が多いからです。
証拠は、すぐに取り調べができるものに限られます。
証拠の提出は、あなたがやらなければなりません。
証拠となるものは、コピーを取って訴状と一緒に裁判所に提出します。
裁判所用と相手用に2部必要です。
原本は審理当日に持っていきます。
主な証拠の内容
(売掛金・売買代金)
納品書、請求書、受領書、領収書、契約書、銀行振り込み用紙など
(敷金返還)
賃貸借契約書、精算書、領収書など
(給料、解雇手当)
給料明細、タイムカード、出勤簿、求人広告、社内規定など
証人
審理当日に簡易裁判所に来てもらえる人に限ります。
|
|
未成年者は?
|
|
原則として未成年者が訴える(原告となる)ことはできません。 結婚をしていれば認められます(成年擬制)が、通常は原告の法定代理人(親など)が行います。
|
|
少額訴訟の手数料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 訴訟額(請求金額) |
手数料(収入印紙の額) |
| 〜10万円 |
1,000円 |
| 10万円超〜20万円 |
2,000円 |
| 20万円超〜30万円 |
3,000円 |
| 30万円超〜40万円 |
4,000円 |
| 40万円超〜50万円 |
5,000円 |
| 50万円超〜60万円 |
6,000円 |
|
|
|
この他に、郵便切手や、法人の場合の商業登記簿の交付手数料、書類の送料がかかります。
郵便切手は、裁判所から相手に書留郵便などで書類を送る費用が必要になりますが、多くても5千円前後です。各裁判所によって多少違いますので、各裁判所で確認してください。
時効の停止や事実確認のためにも、内容証明郵便を事前に出すことをお勧め致します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
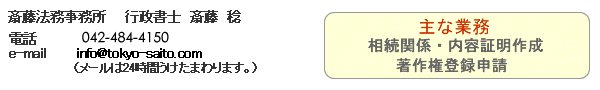 |
|
|
 |
|
|特定商取引法に基づく表記|プライバシーポリシー|免責事項|料金表|はじめての方|自己紹介|
|相続関係|内容証明作成|著作権登録申請| |
|
|
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|